

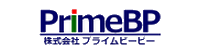
プライムビーピーのホームページにお越し頂きまして、誠に有難うございます。
ビジネスを取り巻く環境は、ITを始めとする新分野の台頭と共に、既存産業や社会経済制度の構造改革という激しい変化に晒されている状況にあります。
また環境問題や少子高齢化という未経験の領域が将来に亘り横たわり、経営の舵取りは益々難しい現状にあると言えます。
こうした中、インターネットを中心とする新しい情報インフラの浸透は、IT産業のみならず既存産業においても社会ニーズの変化に対応した様々なチャンスと新たなビジネス、サービスを生み出してきています。またマーケティングや物流、そして経営戦略のツールとしても効果の高いシステムが実現され、IT技術は不透明なビジネス環境の中にあって不可欠な役割を経営に対して果たすようになりました。
一方、IT化効果への期待に反して情報化の現場では、プロジェクト運営の躓きや導入システムの業務適合性の欠如など、多くの課題が発生していることも事実です。ERPやパッケージソフトウエアの普及が逆に設計技術の低下、そしてシステム技術者の育成の妨げになっていることが指摘され始めています。それは、パッケージソフトの機能に業務を合わせることを前提とするため業務への深い理解が蓄積されない、パッケージの修正に終始し一からシステムを設計する機会が少ないなどが原因となっているものと思われます。
プライムビーピーは、「実務実践」を基本に、豊富な実務経験に基づく業務の視点に立ったシステム化を通じて、様々な経営課題の解決のご提案、ご支援を致しております。IT技術も業務に対しての有効性が低ければ過剰な投資となってしまいます。業務とIT技術を効果的に融合させることが問題解決、システム化目標の実現には不可欠と考えます。そして、そのために、常にお客様と一体となった業務の視点からの取組み、密接なコミュニケーションに基づくお客様ニーズの共有、最適な問題解決とIT化のご提案をすることが、私共の使命と任じております。
| 商号 | 株式会社プライムビーピー |
| 住所 | 〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-25-3 ファインズコート北新宿3F |
| TEL | 03-3362-3033 |
| FAX | 03-3362-3011 |
| 設立 | 平成14年9月24日 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 事業内容 | コンサルティング事業 システム設計・構築・保守などソフトウェア開発事業 ASP開発運営事業 アプリケーションパッケージ開発販売事業 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 多磨信用金庫 |
| その他 | 一般労働者派遣事業許可 許可番号/派13-306513 |
| 平成14年 9月 | 株式会社建設経営サービスの出資を得て、株式会社プライムビーピー設立日本で始めて独立会計方式JV工事会計システムの開発先行型ベンチャーとして事業を開始。 |
| 平成14年12月 | 東京都より創造的事業活動促進法の認定。 |
| 平成14年12月 | 東京都経営革新計画法の認定。 |
| 平成15年10月 | 独立型JV工事会計システム「JV-PACK」の開発を完了し、事業開始。 |
| 平成16年4月 | システムソリューション事業開始。 |
| 平成19年10月 | ソフトウェアセンター(八戸市)の開設。 |
| 平成19年10月 | 青森県並びに八戸市との間で立地協定の調印。 |
| 平成22年2月 | 「東北IT経営実践ファインアシスト賞」を受賞。 |
| 平成23年4月 | 新宿区西新宿へ事務所を移転。 |
| 2023/11/01 | ロケ防のインスタグラムを始めました。 |
| 2023/05/29 | 「わかりやすいJVの運営と会計実務」を出版しました。 |
| 2022/12/15 | 「ホラールーム」は「CAAD」57号(6ページ)のゲーム雑誌に紹介されました! |
| 2022/11/01 | LOCABOをリリースしました |
| 2020/07/22 | PostCeremonyをリリースしました |
| 2018/10/11 | 企業体情報を更新しました |
| 2018/03/02 | ピタゴラロジックが商標登録されました |
| 2018/01/12 | DocuPack with IOTをリリース |
| 2017/10/03 | ピタゴラロジック公開版リリース開始 |
| 全方位型ドキュメント管理システム | JV工事会計システム | LINEBot開発 |
|---|---|---|
| DocuPack 詳細はこちらへ |
JVPACK-LiteS 詳細はこちらへ |
LOCABOはこちら(LINE @821gpjud) |
 |
 |
PostCeremonyサンプルはこちら LINEホラーはこちら 
|
| パンフレット | パンフレット | スペインのアドベンチャーゲーム雑誌 「CAAD」57号に紹介されました!  |
|
ドキュメント管理の基本となるセキュリティ、版管理、検索等の機能に加え、業務運用を考慮した「業務メニュー」を実装し、使いやすさを追求したシステムとなっています。またモバイル利用や地図連携表示、名刺スキャナソフトとの連携等々のオプションも豊富に取り揃え、企業のドキュメント管理を強化します。 |
JVPACKをソフトウエアサービスとしてリニューアルしました。ソフトウエアをお買い頂くのではなく、JV工事1件毎の利用料をお支払頂くようになりました。工期や規模に関係なく、1件分の利用料で開始から決算、精算までお使い頂けます。インターネットを通じて、運用や業務のサポートも受けられますので、安心してご利用頂けます。 |
LINEを利用した様々なシステムを開発します。 |
| 中小建設会社のためのわかりやすい | 工事進行基準システム | ロジックトレーニング |
| JVの運営と会計実務 a |
emi-system A |
ピタゴラロジック 詳細はこちらへ |
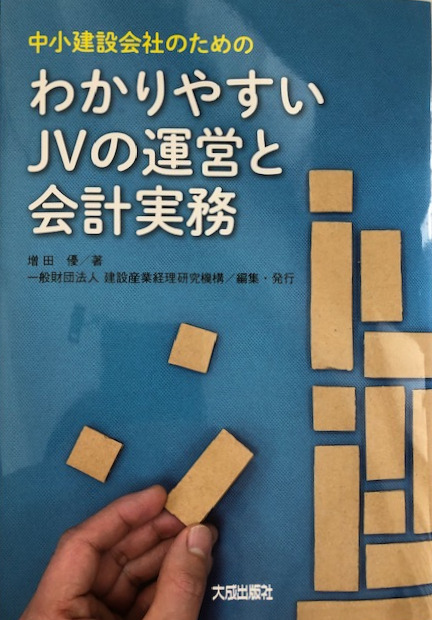 |
 |
 |
| パンフレット | ||
|
JVの運営と会計を実務的に扱った初めての書籍です。共同企業体協定書から運営規則に至る実務面での考え方、JV運営に必要な検討事項などを網羅しています。 |
「emi-system」は、建設業の経営管理業務である進行基準ベースの出来高管理システムを、中小向けに簡易に行えるように工夫しており、月次の工事収益を進捗状況の写真などの画像や資料と合わせて管理できます。大きな特徴として蓄積された出来高情報を活用して標準出来高を作成でき、個別の工事に利用した出来高計画の作成と実績管理を簡単に行えます。またデータ出力により出来高計画を利用した工事の資金計画にも活用頂けます。将来の工事収益の予測管理やグラフを用いたビジュアルな管理など中小建設会社様の経営を強力にサポートします。 |
プログラミング力、システム開発力、そして問題解決力のベースとして重要なのはロジックを組み立てる力にあるとの考えの元に、独自に作り上げた研修用教材です。 |
これほどの地盤沈下を目の当たりにすることはそうないのかもしれない。
建設会社の現況は徐々に緩み、沈んでいく泥土の上に立つ様だ。
このぬかるみからの脱出は今後、「業態変革」を目指す経営的な取り組みとならざるをえない。
一人親方のワンマン会社は、その眼力をあてに力ずくで経営の舵を切る。
代を重ね、世に言う老舗と言われる会社は、危機対策が空回りしている。
いずれも初めて経験する本格的な競争社会の中で、戸惑う姿なのかもしいれない。
その結果は誰にも分からないが、市場は、本来参加者の責任により構成されるものであり、事業の選択は企業個々が判断する。
市場での立ち振る舞いは自由であるとともに、自己責任が基本だ。
戦後の復興から全国総合計画が国づくりの総合プランとして策定され、建設会社には疑いのないビジョンがあった。
約束された技術を保有し、約束された仕事があった。
本社、支店、子会社が同じ技術を使い、同じ仕事をした。
違いは請負う工事の規模ぐらい。
でも、もうない。
よく考えてみると、建設産業にはビジョンも、方針も、理念も、そして日常の業務システムや行動規範まで用意されていなかった。
この何十年もの間、建設業界のビジネスフローはまったく変わっていないのだ。
そこから脱出を試みる経営者も現れ始めたが、自由に戸惑う人の方が多い。
実は経営改革への取り組みは、そんな状況をとらえる視点から始まるのではないだろうか。
中小建設業者の経営計画をみると、中期計画として予算目標といった定量計画が主で、経営政策がまったく含まれていない。
市場の変化を十分に熟考したものではなく、あくまで経営が成り立つための目標値を示しただけだ。
これでは、絵に描いた餅になる。
いま求められているのは、経営改革へ向けた新規事業の具体化や経営課題の実現方策を具体的に示せるかという点だ。
これまでの経営計画は計画と実行、目的と手段が混同されていた。
計画の策定が目的となり、それを実行する具体策が描き切れていない。
さらに言えば、結果こそがすべてであって、各施策はあくまで過程にすぎない。
企業業績の改善と、コストダウンなど経営課題の解決が最終目標なのだ。
例え経営計画などなくても、業績が良ければ企業経営にとって何の問題もない。
業績を向上させること、企業はその一点に経営資源やノウハウを今こそ集中させるべきなのだ。
建設会社は経営者不在と言われる。
産業文化や近代化の遅れを指摘する人もいる。
正確に言えば、遅れているのではなく、止まっていたのだ。
遅れとは流れの中にあってのことで、止まっていたから動きだそうとしても足はもつれ、筋力が足りない。
行政は供給過剰構造を直視し、その改善に向け、動きだしている。
受注競争のハードルを上げ、企業を評価する物差しを変える。
こうした動きが今後、確実に進んでいく。
供給過剰状態を解消するためには、競争環境をより高めるのが、一番の近道だからだ。
そうした環境の中で、中小建設業者は、どのようにした生き残りを図るのか。
そのヒントが生活者の視点で外を見渡すことだ。
発注者ではなく、エンドユーザー(納税者)のニーズを見ることだ。
だが、そのニーズは建設業界のテーマではないのかもしれない。
だが、そこであきらめてしまうと、新たなビジネスを開くことはできない。
もともと建設会社は地場産業として地域に密着し、生活の視点を共有していた。
地域が求める社会資本を整備していたからだ。
今だって地域コミュニティーが必要としているものが、必ずあるはずだ。
それを建設会社がどこまで取り込むことができるかが勝負だ。
魅力ある産業は、決して市場の大きさだけを指すものではない。
産業自体に動きがあり、鼓動があればその振動に回りも呼応する。
改革への志があれば、人が集まり相乗が生まれる。
魅力的な産業と言われるような新しいビジネスモデルをつくり出す。
経営改革とは、そういうものだ。
2003年4月14日(月)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
一時のITブームも去り、e-ビジネスともてはやされたIT系のベンチャー企業はもとより既存の事業会社によるITを活用した新たなビジネスモデル化への取り組みも平静を取り戻した感がある。
ブームに乗っただけのリアリティを欠く事業モデルは既に見受けられなくなった。
しかしながらインターネットの普及には目覚しいものがあり、仮想商店街やサイバー広告など堅実にその地歩を固めたビジネスモデルも数多い。
企業のネットワーク環境もクローズされた通信網から完全にインターネットをベースとするものへ取って代わってしまった。
コミュニケーション手段としてのグループウエアの社内導入やEメールによる社外との連絡も今や当たり前の道具となっている。
メールアドレスの記載されていない名刺は珍しいほどだ。
先進的な企業はインターネットをベースとするシステムへ適合するよう業務プロセスの改革を始めている。
またインターネットを通じてこれまで入手や取り纏めに苦労した情報の多くが手に入る。
低コストで広く共通の手段として利用できるインターネットは今後益々発展していくものと考えられる。
建設業界に目を転じると、インターネットの普及と共に大手建設会社を中心にホームページの公開や協力会社のネット公募などが始まった。
建設資材だけではなく外注発注も含めたマーケットプレイスも登場するなどインターネットの可能性を期待させるものであった。
建設のポータルサイトを目指すものや、建設現場におけるプロジェクトマネジメント力の強化を狙ったシステムサービスなど様々なインターネット活用も試みられた。
しかしながらネットブームの終焉と共に一時の盛り上がりを欠きつつある。
その理由には業務適合性の課題や建設会社の情報基盤の未整備、情報リテラシーの不足など様々な意見がある。
確かに、建設会社の市場競争力のひとつに「価格」がある中、コストがガラス張りの米国に倣ったマーケットプレイスが成り立つかどうかは当初より疑問視されていた。
また建設資材の商流は思いのほか強固だ。
一般消費財のような商流改革は進み難い。
可動性が高く労働集約型の産業におけるIT化の限界も指摘された。
手間仕事を任せるための担保は実ビジネスでは相当重い。
現在ネット公募を継続している会社は半分あるか。
大手建設会社を中心にいまIT投資へ振り向けられてられているのは、従来の業務形態をインターネット上で利用可能とする置き換え処理と言える。
例えば電子購買と言えば聞こえは良いが、ペーパーの電子化。
それでも省力化効果は大きい。
大手には実を取る力がある。
残念なのは、名刺に刷り込まれたアドレスへ送ったメールに返事が来ないように、中堅中小の建設各社が得たその実の少ないことだ。
メールにもビジネスの礼節やルールもある。
ネットブームは一時のお祭りの面も確かにあったが、建設業へのいくつかの提案がなされたと考えられないか。
何ができて何が足りないか。
そして将来へ何を実現するか。
取るべき実は多かった筈だ。
建設業界に複数のネット調達のサイトが立ち上がりつつあった時、サプライヤーから出された批判は、複数のサイトへ参加することの手間と非効率に対してだった。
ひとつのサイトへ入れば全てに対応できるようサイト側で解決してほしいと言うものだ。
つまり面倒を掛けずに公平に皆が参加できる環境づくりを願う。
発注者による電子入札においても同様の要望があった。
本来サイトの主催者(バイヤーとしてのサイトの利用者)は、競争原理を働かせ低コストで高い品質の獲得を期待している。
その中に残れるサプライヤーのみが競争の勝利者となるし、サイトの主催者も自社のサイトが優れた市場を形成することで、自社のビジネスの勝者となる。
つまりサイト自体の競争力を高めることも重要となる。
バイヤーが競争に勝ち残るための道具として主催したのがサイトであり、この当たり前な目的が理解の内にない。
確かに市場への参加は競争の意思あるものには公平が基本だ。
但し手間の省力化と効率化はサプライヤーの経営努力でなければならない。
それも期待された競争力のひとつだからだ。
返事のないアドレスには二度と誘いは来ない。
2003年5月6日(火)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
建設に関連したファイナンススキームが多様化している。
金融システム改革と言われた国際化・自由化(金融ビックバン)の結果様々な金融商品の登場や市場型の間接金融の増加が建設へ波及してきているからだ。
建設はもともとファイナンス機能を持った事業と言われてきた。
しかしながら商社が商品の流通過程で発生する与信や決済を商社金融と称し明示的にビジネス機能として位置付けてきたのに比べて、建設ではあまり目立たぬ存在であった。
建設会社は一般に前途金、中間金、竣工金の3段階で発注者から工事代金の支払を受ける。
その間自己資金を用いて毎月の出来高、納品等に応じて協力会社への支払を行う。
このキャッシュフローの差が建設会社におけるファイナンス機能の原型だ。
これまでも建設業では個別の事業にのみ使途を限定し、当該事業からの収益により資金回収を行うプロジェクトファイナンスや、造注のための付加サービスとしての建設資金の立替や債務保証等が行われてきた。
また高度な事例としてB・O・T(ビルド・オペレーション・トランスファー)方式による事業運営を通じて建設資金を回収するスキームにも実績がある。
最近ではPFI(プライベートファイナンスイニシアティブ)が一般化し、公共性の高い事業の建設及び運営方式として定着しつつある。
こうした資金スキームは、建設事業におけるファイナンスに請負者である建設会社が主体的に関わるものだ。
2000年のSPC法の制定と投信法の改正で不動産投信(REIT)のための制度が整備されたことにより、不動産の証券化も大いに進んでいる。
土地再開発事業では今やSPC設立が当たり前だ。
新築マンション建設の事業スキームとして証券化を導入するケースもでてきた。
変り種では家賃補償をファンド化した共済制度もあると聞く。
一方、建設の事業ファイナンスに加えて、先にファイナンス機能の原型と呼んだ工事を請け負った以後の建設ファイナンスでもここへきて様々な取組みが進みつつある。
支払手形の発行を廃止し、ファクタリングを導入する例は珍しくない。
手形の代わりに期日指定(例えば90日後など)の現金支払を約す支払形態もある。
更に進んで大手ハウスメーカーでは、金融機関と共同でインターネットを用いた決済システムを導入し、協力会社が期日指定日前に支払金額を手形のように割り引いて現金化できる仕組みを導入している。
また別のハウスメーカーでは個人の施主向けに出来高払いのローンを損害保険会社と共同開発した。
施主は住宅建築のつなぎ資金が不要となり、工事進捗に応じた融資を受け、そのまま工務店等へ支払われる。
出来高払いの効果については国土交通省も研究課題としていると言う。
こうした様々な建設事業に関わるファイナンススキームの多様化は建設経営にも建設産業にも多くの変革をもたらすだろう。
元々建設事業は多額の資金を必要とし、事業主の資金力と共に、請負企業である建設会社の信用力と隠れたファイナンス力に支えられてきた。
そうしたファイナンス機能が請負契約(ゼネラルコントラクト)に暗に含まれることなく切り離され、明確に建設サービスとして位置付けられる意味合いは大きい。
サービスならその質が競われるからだ。
それは顧客ニーズと相まって事業内容に適したメニューの開発や間接金融としての流通市場の創造へと発展していく可能性を秘める。
更に公共事業自体においてもプロジェクトファイナンスの導入、民間ファンドの設立や資産証券化など資金スキームを多様化させていくであろう。
工事毎にファイナンススキームが組み込まれれば、会社としての資金管理の考え方は大きく変わる。
例えば元請建設会社による支払保証と協力会社のファクタリングの組み合わせは工事施工途中における元請建設会社の工事資金を不要にする。
資金決済の仕組みが変われば建設会社に毎月訪れる作業負荷の大きな定時支払業務はなくなるかもしれない。
建設会社のビジネスプロセスは大きく変わるだろう。
金融の多様化は上場企業だけではない多くの建設会社に対する様々な評価の必要性を高め、技術力や施工品質、経営面での取組みが反映される企業格付が発展する可能性を生む。
また単に一企業の財務面や経営面での評価だけではなく、請け負った工事の発注者やその事業性により工事毎の資金コストが変わるような仕組みも実現性はある筈だ。
市場の中で正当に評価され明示される基準が生まれる効果は大きい。
公共工事では下請セフティーネット等の一部の例外を除いて認められてはいないが、工事債権の流動化や譲渡債権を認めることも、新たな建設ファイナンスの可能性を開くことにもなろう。
こうした建設ファイナンスへの取組みは、業界全体として行っていく大きな課題と共に、先の事例のように個々の建設会社の経営努力により実現可能なテーマも多い。
いずれこの隠れがちな機能が新しい建設のビジネスモデルの創造に不可欠な要件となるものと考えている。
2003年6月4日(水)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
どの産業にもその産業を性格付けている共通の文化、体質というものがある。
そしてどの会社のどの部署でもその体質が少なからず感じ取れるものだが、特に色濃くその産業体質を体現した業務が営業と言えるだろう。
その上営業は商売の原点だ。
故に、制度疲労や経営環境の変化に直面した多くの会社で営業改革は欠くことのできない重要な経営革新のターゲットとなる。
目に見える体質改善の象徴となるからか。
商品、制度、システム、マインド様々な角度から改革の一刺しを起案する。
建設産業ではよく指摘される請負体質がそれだ。
その思考回路に組み込まれたロジックは建設営業の行動原理に特徴的だ。
チャレンジを始めた建設会社のネックが意識改革のできない営業部門となることも多いと聞く。
経営者が、すっかり入れ替えてしまった会社もあると言う。
これまで建設会社の営業がお世辞にも花形部門となったことはなかった。
公共工事は寄り合いで、民間工事はトップ営業が原則だ。
バブル経済に突入する前、しばらく建設は冬の時代を過ごし、建設各社は「全社営業」「造注」を御旗に、営業を全面に押し出す。
民間営業が大世帯となった。
今でこそマンション建築は当たり前だが、昔は老舗のゼンコンの肴ではなかった。
それが今ではデベロッパーも自前でこなす。
時代のニーズも事業スキームも変わってきている。
けだし、請負体質は変わらない。
デベロッパー事業も工事を請け負うための視点ばかりで、事業を見渡す目利きが不足している。
形ばかりの事業収支が積み上げられた。
比して工事の実行予算は適切だ。
販売用不動産は資産勘定に鎮座している。
建設会社には隠れた負の遺産も多い。
勇んで取り組んだ住宅フランチャイズの権利金に、使わぬ技術パテント、企画マンションの商品開発コスト。
市場を読み間違えたか、目的を迷ったか。
ここにも請負体質が顔を出す。
セールスは古今東西工夫の賜物、リトライと反省を糧に実績を作っていくもの。
こっちでは営業が鎮座ましている。
自社のシェアは幾ばくか。
つまりは負けているのだ。
それを捨て、あれを捨て、では行く先は危うい。
何も新技術、新企画に頼らずともネタはある。
顧客ニーズとは言葉ばかりでなく、商品やサービスの中に自然に加えていくことはできないか。
発注者や事業者の先に、本当のニーズがある。
そこに利用者がいる。
自らサービス事業の主となった建設会社の設計部門が育った。
社員総出で事業運営に参加している。
その事業を通じて施設のメンテナンスや利便性を自ら体現し、様々な設計に反映しているからだ。
施設利用を踏まえた設計の重要性を痛感したと言う。
地域や顧客との永い付き合いが地場産業の信条、建設の原点には地域のニーズを汲み取る力があった筈。
ひと肌もふた肌も脱いでいた時代はいずこ。
業態転換も選択枝ではあるが、延長戦上にも実りはある。
そのためには収穫への働きかけが必要だ。
待つ営業から創りだす営業へ、それは請負体質からの自己改革でなければ得られない。
物件を探し、顧客を探し徘徊する営業から、地域を知って、ニーズを知った営業へ。
市場を掘り起こそう。
役所へ提案して廻る会社もある。
ニーズや課題のあるところに場違いなどない。
組織営業、システム営業の御旗は掲げられてからどれだけ経過しただろうか。
大事なのは情報の共有。
餌場を一人で抱えているのが一匹狼。
ネアンデルタール人が絶滅し、体も力も劣るクロマニオン人が生存競争に勝ち得た理由は言葉にあった。
クロマニオン人は餌場を言葉で記憶し共有できた。
ある地方ゼネコンのトップは、引き合い情報の開示に力を振るった。
事前に引き合い情報が報告されていない案件を受注しても営業担当者の成果とはしない。
新規顧客への対応は複数であたる。
風通しが格段に違った。
営業改革は、正に戦のフロントライン、経営トップが先陣切るのが慣わし。
人任せ、批評家側に立っては、事は進まない。
社員は観ている、感じている。
新たな企業風土、文化形成の時、旧弊を捨てたトップも多いと聞く、本丸と定めたか。
もう右肩上がりでないことは誰でも知っている。
順番を待っている時ではない。
市場は同じものには優劣をつけまい。
大事なのは自社の言葉で、自社の腕で形創ること。
でなければ長続きしない。
人真似も場所を変えれば時間稼ぎぐらいにはなるか。
志のあり様は違う筈だ。
足で稼ぐことも必要かもしれない。
しかし聞くのは顧客の声、世間の声、時代の声。
声のするところに姿は見えるもの。
2003年7月31日(木)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
建設業におけるIT導入も多岐に亘るようになり、多くの業務情報及び業務処理が電子化されている。
技術計算やCAD、会計業務などの基幹系業務は勿論、情報系と称されるグループウエアの導入も規模を問わず当たり前となりつつある。
IT化しやすい特定の業務に従事する人だけではなく、ITと建設会社の社員との付き合いは既に長く、そして広範囲となっている。
一方、こうしたIT化が浸透しつつある状況にも係わらず、未だ推進におけるトラブルは尽きない。
コストアップは当たり前、当初費用の3倍にもなったとの話も聞く。
新システムの構築に幾度もトライして纏まり切らずにいる会社もある。
システム仕様が収まらず二転三転する話はこと欠かない。
それも計画済みとするのが常識となりつつある。
確かに建設業の業務知識を欠いたシステム技術者が多いことは大きな課題のひとつだ。
会計伝票一枚書いたことのない技術者の設計したシステムの運用が覚束ないのは当たり前と言える。
そこでパッケージシステムをベースに寄せ集め、建設業務或いは個々の企業特有のシステム機能に修正、付加するイージーオーダーのような取組みも多く行われる。
しかしてなかなか体にフィットせず、掛かる手間が変わらないのが現実だ。
例えば建設業会計という仕組みは制度会計と一体となって体系化されており、そのため一から建設業の会計システムを設計する場合には、言わば制度会計の体系の中へ組み込んだ会計組織としてデザインする。
従って一般化させた制度会計のパッケージシステムとはどうしても親和性が低くなってしまう。
一事が万事、建設業務の全てにそうした深みがある。
いずれにしても建設業の特異性に対してIT業界における対応が充分とは言えないが、はたして建設業サイドには問題はないのだろうか。
多くのトラブルにおいて、システムベンダーの力不足ばかりが問われるが、そこには過分にスケープゴートとされている点も見過ごすわけにはいかない。
必要なのは問題解決であり、責任追及ではない。
IT化の推進はシステムベンダーと導入企業との信頼関係に根ざしたパートナーシップによって始めて実現する共同作業だからだ。
目にあまるベンダーも確かに多いが、建設会社が毅然とした対応を怠るために締まりのないプロジェクト運営にしてしまっていることも多い。
常にバランス感覚と成熟を意識することが第一に求められる。
IT化は、特に基幹系の大規模なシステム開発の場合には、推進のプロジェクト体制も規模が大きくなり、当然その活動期間も長い。
プロジェクトが一つの目標実現に向かうのは建設事業もIT化も変わるものではない。
そこで、IT導入で重要な導入企業側の要件とその裏腹にある課題を、COMPUTERのスペルになぞって捉えてみた。
CはCommunicationである。
情報化推進のプロジェクト内がシステムベンダーを含めて一体感を持つためには良好なコミュニケーションは当然と言える。
システムベンダーとIT化の原価企画を一緒にできるぐらいの協調が図れるのが理想だ。
更にプロジェクトの外、つまり関連部門や現場、当然経営者とも適切なコミュニケーションを維持することが大切となる。
社内が遠巻きにプロジェクト運営を眺めているような推進であっては、成功は覚束ない。
常にオープンに情報を開示し、積極的なコミュニケーションを図ることで信頼関係が構築され、プロジェクトへのシンパシー、協力が生まれる。
こうした努力なくしてプロジェクトへの社内の信頼感、システム化によるBPRへの心情的な抵抗を和らげることはできない。
ともすると前方位のコミュニケーションは建設業にとって苦手な分野だが、円滑なプロジェクト運営には不可欠な要素と言える。
IT化推進で一番重要であるにも関わらず不明瞭であることの多いのがObjective(目標)かもしれない。
業務生産性の向上、間接業務の自動化とコストダウン、ペーパーレス化に高度な情報活用の実現、云々云々、耳障りのよい目標が列挙される。
こうした蓋然的な目標設定によりUpset(目的と手段の混同)が生じてしまう。
つまりIT化自体が目的化してしまい、実現すべき本来の目標が見失われていく。
目標の基本はできる限り定量化されなければならない。
例えば「ペーパーレス」を挙げるのであれば(それ自体が最終の目標とは思えないが)、少なくともシステムから定型的にアウトプットするレポートを法定帳簿と主要な管理帳票のうち数種類に限ってしまうぐらいの数値設定を期待したい。
IT化推進はITを活用した目標の実現の場であり、IT化自体ではない。
目標を実現するシステムの構築を行う上で重要な設計のプロセスがRequirement(業務要件定義)である。
業務として必要な要件を機能、情報、フロー等の面から定義づけていく。
この作業が正に業務改善であり、新しいビジネスプロセスと仕事の仕方をデザインする。
しっかりとした業務知識及び業務の関連に対する理解を前提とするため、導入企業の重要な役目だ。
この業務デザイン如何が後のシステム化のための作業を定義付けるため、システム仕様が固まらない多くのトラブルがこの作業に起因する。
仕事の精度が要求されるのだ。
IT化推進のプロジェクト運営では、当然そのManagement(マネジメント)力によるところが大きい。
プロジェクト運営の大きなテーマがTime(スケジュール管理)と先に挙げたCommunicationに裏つけられた交渉力にあることは建設における現場運営と変わらない。
ステコン(ステアリングコミッティー/経営トップを長とする情報化推進委員会)と称するプロジェクトの上位に位置する意思決定組織を設置するケースは多い。
外資系企業に習った組織運営だが、はたして日本の組織風土に馴染んでいるのだろうか。
屋上奥を重ねるだけならやめた方がよい。
プロジェクトリーダーの仕事は汗をかくこと。
大人の差配も必要だ。
役員室を走り回る熱いEnergy(成功へのエネルギー)は欠かせない、何よりプロジェクトメンバーに伝播する。
職業人として、組織人として、IT化推進のプロジェクトに配置され、会社の全般を見渡す機会を得られる方々の数は決して多いわけではない。
数少ないチャンス、粗末にしてはいけない。
会社というのは広く深い存在、丁寧に、そして大胆に関わるのが基本。
組織をいじり、仕組みをいじる恍惚と不安と。
辛い仕事だからこそPleasureが基本姿勢。
COMPUTERが揃うことがIT化かもしれない。
2003年8月26日(火)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
「経理財務業務マップ」をご存知だろうか。
経済産業省が今年の3月に発表した「企業の経理財務部門で行われている業務の全体像を記述した」職務体系である。
「業務マップ」は、BPR(業務の設計)や人材育成、そして職能評価等に活用することを狙いとし、体系的網羅的に経理財務業務を取り纏めている。
作成の背景として、経理部門が従来の会計情報を作成することから、会計情報を分析し、経営への提案機能を高めることへとその役割が変化してきていることを挙げている。
「戦略的な経理財務部門の育成が円滑な事業活動を展開する上でも重要であると再認識されている」ことが基本にある。
企業会計は人の神経のように営業活動で発生した様々な経済取引を知覚(記述)するものと言える。
神経が多岐に張り巡らされ様々な行動を支えているように、企業会計もより企業活動の全体像を捉えていく方向にある。
国際会計基準に沿った実質支配に基づく連結決算や、税効果、減損会計等々の制度会計における厳格な計算と開示への要求もその本質には企業が知覚すべき事象を拡張し、企業会計がジェネリック(集合として)に企業を捉えることを可能にしようとするものだ。
よって会計情報の網羅性や視認性は高まり、経営への提案力が向上する。
また会計の役割は、公共団体や公団等への企業財務の導入という面でも進みつつある。
従来の収入と支出だけで捉える公共系の組織・法人の公共会計から民間企業同様の財務諸表を作成することで、財政並びに損益を計算し経済性を評価しようとする試みだ。
公共サービスや事業の結果を効率性や収益性といった面からパフォーマンス(成果)として捉える必要性が根本にある。
このように会計が非常にクローズアップされている時代ではないだろうか。
経済社会の中で会計の持つ社会的な存在意義が大きくなっているからだ。
一方で一般に会計への理解が不足しているのも事実である。
未だ多くの会社で会計の役割は計算の域を出ない。
特に建設業はもともと技術主導型の産業のため財務会計が軽んじられてきた面がある。
「たかが経理」と言う経営者も少なくない。
当然ながら経営者の愛情の足りない経理部門が育つわけがない。
そこには集計、計算事務以上の期待がないからだ。
それどころか化粧を施された経理数値で社内の経営報告がなされている会社も多い。
担当者が代々伝承された化粧の訳も知らずにいたという笑えない話さえあるほどだ。
いわんや経営者が自社の会計数値を正確に理解できているはずがない。
経験と勘が羅針盤の経営に唯一制度化され、共通のそして定量的な情報を提供できるのは会計しかない。
また会計というのは様々な企業活動を記録するものであり、会計情報として多くの付帯情報を把握、蓄積することも可能だ。
またそうした実績情報は様々な傾向や示唆を与えてくれる。
目標として掲げられることの多い「先行管理の実現」とは、実はそうした実績の積み重ねの上に成り立つ。
一足飛びに先々の予測などできない。
国際化の波は国際会計の導入に相俟って今後益々新たな会計面でのテーマを投げかけてこよう。
当初工事進行基準の導入に抵抗していた建設業界は、減損会計の強制適用に際して収益嵩上げの手段とみると積極的に採用した。
そして四半期決算の開示を迎え、工事進行基準の適切な運用が課題となった。
また反旗が掲げられるのだろう。
国土交通省が決定した共同企業体の独立会計方式導入への業界対応も同様に、本質を外れた小手先のその場凌ぎを示し合わせる。
しかし銃後には連結会計の視点から持分会計がテーマとして待っている。
消極的な後手の対応はいずれそのフロントラインを突破されてしまうのが世の常。
世にJV会計への不信の目があることを忘れてはいけない。
横並びで契りを結んで良しとする業界体質は、右肩上がりでなくなった時代には綻びだすだろう。
本来なら大手企業としての矜持と先導役の徳を期待されるところ。
率先して新しい企業経営に相応しい会計を研究、実務導入することで中小、地方ゼネコンの範となることを。
国際会計への対応は上場建設会社だけではなくやがて中堅中小へも浸透していく。
そこにある大きな成果はグローバルスタンダードの導入自体ではなく、国際会計の求める役割を担える企業会計のレベルアップとその結果としての経営の強化にある。
それはまた経理財務担当者の企業経営における存在意義の向上でもある。
時代に相応しい経理部門を創り上げることを経営目標とする建設会社は何社あるだろうか?
2003年9月8日(月)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
1997年をピークに建設産業就業者の減少が続いている。
バブル崩壊以降建設産業の低迷が続いていたにも関わらず建設就業者は増加傾向にあった。
今年4月の調査では591万人とほぼ1990年と同等の規模となっている。
この間建設業界では大手を始め地方においても多くの建設会社がリストラに取り組み社員を減らし続けている。
厚生労働省の労働経済調査においても常雇労働者の過剰感は建設産業がトップであり、未だ高いDI(指標)を示している。
一方、一部の大手建設会社を除き業績回復の兆しは見えず、多くの建設会社にとってリストラの痛みが癒えぬ内に更なる努力を強いられている状況にあるのではないだろうか。
持久戦の様相も予想される中、リストラによる様々な弊害も生じている。
人員削減で計算上のコスト圧縮はできたが、その見返りは思いのほか将来に対して大きい。
建設産業は以前から人の産業と言われてきた。
労働集約型産業ゆえに機械化や自動化の範囲が限られ、どうしても人の経験とノウハウに依存する部分は大きい。
つまりばっさり切った後には何も残っていなかったという話になる。
これは営業や管理も含め全ての仕事に同じ。
手帳も名簿も個人の所有物と気付くやいなや会社の組織制度やシステムの重要性を思い知ることになる。
慌てたSFA(営業支援システム)導入の動機がここにあった例は多い。
ノウハウの伝承と言われる社内徒弟制はどこの建設会社でも見られるが、実はこうした状況へのセーフティネットにもなっていた。
ところが仕事が減ることで人の脈も切断されていく。
土木が著しいという。
一人前になるには経験も経験を積むための機会も必要。
若手の力不足が明らかとなる。
老害への批判を繰り返してきた若手が、重石が外れていざ責任者となると仕事が形にならない。
訓練されていなかった。
こちらは若害だ。
影響が見えにくいのでトップがしっかりと世話しなければいけない。
よく考えるべきは物事の道理。
これまでの仕事のやり方でよいなら経験も貫禄も必要、老害より若害の影響が深刻だ。
仕事の仕方を変えるなら若手に伸び伸びやらせよ、お金も権限も付けて、また少し目も瞑って。
その場しのぎのリストラとその結果としてのポリシーのない若手の登用ほど会社を悪くするものはない。
また現状維持でのリストラの影響は仕事の質の低下も招いている。
人が1/3になれば当然出来高は上がらない。
仕事の内容を点検し、仕事そのものもリストラして始めて効果を得られるもの。
バックログ(やり残しの仕事)が積みあがっている会社も多い。
以前なら怒る人、宥める人、誉める人、それぞれに人がいて、人に関わり、会社へのロイヤリティと人材育成そして仕事の質が担保された。
今では一人でこなさねばならない戸惑いを地方ゼネコンの新任課長が嘆いた。
建設会社の事業に目を向けると粗利ベースで10%前後の低収益構造となっている。
国家における建設の目的は権力維持の国土形成、社会基盤づくり。
重要課題ゆえ研究開発も人材育成も国家予算。
手間仕事の建設会社に再投資のための高収益は認めてもらえない。
世も役割も変わり日本の建設会社の技術力やノウハウは世界でも有数となったが変わらぬ収益構造。
建設会社の研究開発投資は蓄財から出す無税償却の範囲内がほとんどではないか。
少々穿った見方かもしれないが人材育成を含めて将来のための再投資に金が回り難いのは事実である。
もっとも建設会社の側にもそうした現状を変える視点が欠けている。
リストラの結果、少なからず大手建設会社にいたベテランが地方ゼネコンへ第二の活躍の場を移した。
初めて知った世間の広さを異口同音に口にする。
同じ会社に居つづけたら感じ得なかったという、一皮もニ皮も剥けたという。
エンジニアにしろ営業にしろ彼らの第二のステージはスペシャリストとしてのミッションだが、引き出しの多い分出てくるものは豊かだ。
一方でどれだけ受け入れた企業が彼らを活用できているのだろうか。
即戦力の人財を柔軟に受け入れることでの企業活性化の方策も必要だが、組織に居続けて人罪とならぬ組織文化や人事も、リストラの延長戦上で考えていかなければならない。
人財がいつまで居てくれるかも経営努力に依る。
2003年10月8日(水)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
建設会社における実行予算管理制度が工事原価の統制手段として定着しているのはよく知られている。
工事毎の原価を工事工種毎に予算化し管理する方法だ。
一般に建設会社における実行予算管理は経営管理の中核をなす制度であり、実行予算を通じた個別工事毎の原価統制を基にしながら会社全体としての利益管理を実現する、シンプルだが優れたシステムとなっている。
個別工事毎の直接的な工事原価に加え間接部門経費を共通経費として組み入れ、更には工事金利を負担させることで、財務計算上の経常利益に見合う利益管理を、実行予算を通して行ってしまう。
つまり各工事が実行予算を堅守すれば企業利益が約束される体系となっている訳だ。
実行予算管理は優れた制度ではあるが、制度としての管理領域には限界がある。
また言うまでもなく制度ないし手法というのは明確な目的を持ってそれを活用することが重要であり、ステレオタイプな導入は逆に労多くして利の少ない結果を生んでしまうことになりかねない。
そこでいろいろな会社の制度を観てきてたいへん気になっている点を取り上げてみたい。
厳しい建設産業の現状の中、減少する工事量に対応してせめて厳しく原価管理を行い、利益確保することは必至である。
そのためにも自社の制度を点検し、より効果あるものへと継続的な改善を図ることが大切だ。
実行予算管理制度には大きく2つの課題があると考えている。
ひとつは実行予算管理イコール原価管理と捉えることである。
2番目は実行予算管理により現場の原価管理ばかりに目が行ってしまい会社トータルで原価統制を行うという視点が失われているということだ。
以上2点を個別に観ていくことにする。
建設会社の実行予算作成は元々発注者(官庁)による建設費用の見積から始まったと言われている。
現在も各社の提出する見積は実行予算に相似だ。
必要に応じていくつかの工種を作業ベースに組替えて実行予算書に書き直す。
いずれにしても単価と数量の組み合わせ。
つまりあくまで予算なのだ。
一般に工事原価の統制は、「単価」については購買交渉、発注ロットの取り纏め、仕入先の開拓及び絞り込み、代替材料等の検討等々、購買がターゲットとなる。
「数量」は設計見直し(VE)、工法検討、段取り、生産性、物流等々、技術や現場運営で取り組む。
正に原価管理の主たる活動だ。
こうした活動の成果が、予算化した原価を保持、更に低減を図るといった予算実績として現れてくるのである。
このことはつまり予算統制は適切な原価管理を促すこと或いは原価企画することであり、それ自体が原価の管理ではないということだ。
例えば「実行予算の作成を義務付け原価管理しているが一向に現場の利益改善が進まない」「実行予算が意味をなさない」「月次単位の実績把握では原価管理にならない」などとよく耳にするが、それは実行予算管理という予算管理制度を導入しているがそれによる予算統制が機能していない、と言っているに過ぎない。
つまり原価管理そのものについては現場任せであり、コスト削減のための現場支援や管理向上のための活動がなされていないのではないだろうか。
原価管理はそれ自体として経験の積み重ねや様々なアイデア、ノウハウ、管理技術等の向上の結果であり、組織化や共有化により高めていくものだ。
逆に予算管理には予算管理のスキルがある。
こうした誤解は特にコンピュータを用いて実行予算データを管理している場合に陥りやすい。
予算のデータ管理が中心となり(或いはそれが目的化してしまい)、原価管理そのものへの取組みが疎かとなりがちだ。
実行予算の管理と共に現場支援の体制を整え、予算管理制度で得られるデータを活用し、有効に原価管理が機能する全体像を捉えることが必要となる。
実行予算管理制度には予算管理と原価管理という大きく2つの機能と目的が含まれており、一般に情報システムとして組み込まれているのは予算管理としての機能である。
原価管理の機能は予算管理の機能と有機的に結びつくよう制度検討することが重要となる。
実行予算管理制度は先に述べたように個々の工事の予算統制を通して会社全体の利益を管理する体系を有している。
このため実行予算管理により個別工事の利益管理さえしっかりしていれば問題ないと考える傾向が強い。
確かに唯一収益の源泉は工事であることから言えば、そこを厳しく統制しておくことは当然だ。
一方で、間接部門や期間経費はどうであろうか。
多くの建設会社が現場へのコストに対する視線に比較して本社や支店等の間接部門へ向ける視力は弱い。
会社全体のコスト構造が見えていない。
一般管理費や貸借対照表にはなにやら溜まっていやしないか。
一般管理費予算のような単年度の予算統制手段の導入はよく見かけるが、期間コストや資産負債を総合的に統制管理する制度の導入は少ない。
共通経費の配賦処理でさえ慣例でやっているだけで、本来の目的が忘れられている。
今建設会社に必要なコストダウン、原価管理は、現場だけではなく、会社トータルとして取組むことにある。
工事の実行予算を含めた会社全体に対するトータルなコスト管理制度を構築することが重要だ。
言葉を変えればコスト統制を通じたマネジメントの復権かもしれない。
予算というのは実行予算であれ、会社のトータルな予算であれ、経営の目標の上で配分や編成の方針が位置付けられている以上、経営目標そのものでなければならない。
そうしたトップの意思を伝達するための制度を創ることが重要だ。
2003年11月10日(水)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
(財)建設経済研究所が発表した予測では、2004年度の名目建設投資は52兆708億円(2003年6月)になるという。
1997年から8年連続のマイナス伸び率を記録することになる。
50兆円前後の建設投資額は「建設冬の時代」と言われた昭和50年代の水準となり、当時は建設業者数、建設就業者数それぞれおよそ51万業者、540万人の産業規模であった。
2003年度の統計では建設業者は55万業者、591万人の就業者数であるから、単純比較だが、4万業者、51万人弱の供給過剰が読み取れる。
また産業構造は大幅に異なり、当時は資本金1千万未満の個人及び零細業者が90%近くを占めていたが、現在は58%弱までに減っている。
法人事業者の割合が増えていることから推察すれば、業者数の過剰感は数字以上と考えられる。
国土交通省は既に産業の再編淘汰へと政策の舵を切っており、確かにそれに呼応するかのように建設会社の相次ぐ倒産や経営破たんが続いている。
しかしながら破たんした建設会社の更正や債権放棄は、逆に破綻企業の健全化が図られていることを意味する。
民事再生中にも関わらず破たんへの危機が回避されたことで、競争力を増して他社の脅威になっている建設会社の話も少なくない。
縮小しているとは言え更正会社も営業活動を継続しており、早期に倒産した建設会社は再生し市場へ復帰してきている。
是非の声があるのは事実だが、こうした状況も現実である。
米国の格付け会社は銀行から債権放棄を受けた日本企業の社債の格付けを高くする方針と言う。
ここ10年あまりで大手ゼネコンは平均して1.2%の対売上高販管費率を改善してきている(建設経済研究所調査)。
金融支援を受けている建設会社だけの平均では2%を超える著しさだ。
淘汰ではなく再生が進んでいる。
また企業再編も政策的に進められているようだが、こちらも統合メリットの少ない産業特性からかなかなか進まないのが実体だ。
破たんしたゼネコンを受け入れるメリットや目的が見えてこない。
異業種転換や新規事業の促進に関しても支援策による行政の後押しは確かに力強い。
公共工事の縮減、とりわけ土木工事の減少は厳しい。
土木技術者の過剰感はどの会社でも大きな課題となっており、建設従事者の他産業への異動は待ったなしの状況だ。
しかしながら建設技術者の職種転換の難しさが現実問題として横たわっていると聞く。
新規事業についてもそう簡単ではなさそうだ。
人材も資金も豊富な他産業の大企業でさえ、様々な新規事業に取り組み、散々な結果となったことは知るところだ。
確かに建設会社は地域に精通し、市場特化型で推進できる強みがある。
それでも様々な面で大企業に勝るとは言えない建設会社が、新規性の高い事業へ軽々に取り組めるものだろうか。
産業規模の縮小には業者数の縮小は必至にも関わらず、実際の成果は上がっていない。
それはつまり市場の競争相手として留まっていることに他ならない。
皮肉にも競争は徒に激しくなる一方だ。
更に、これまで比較的健全であった地場建設会社でも、破綻企業の返り血を浴びて傷つく例が増えてきている。
こうした建設会社は安定的であった分改革意識が低く、脇が甘い。
右肩下がりの経営状況に「ゆで蛙」の例えではないが、健全と言われた企業であっても目が離せない状況になっていくことが懸念される。
産業の淘汰再編も異業種への事業転換や新規事業の推進、これらを否定する理由はなく、縮小を余儀なくされる建設産業には不可欠な取り組みであろう。
但し、忘れてはならないのは建設会社である限りは、建設市場において厳しい競争に勝ち抜くための経営努力を継続的になさなければならないということだ。
つまり建設会社としての本業を深耕し競争力を高めることは当然であり、そこにも再構築の余地が多く残されている。
いや、公共投資に支えられ競争性の欠けた市場として営まれてきた業界で、個々の建設会社には未だ未着手の経営課題や成長への取り組みが多々ある筈だ。
カイゼン活動を不断に続けるトヨタ自動車の成長を自身の経営にしているだろうか。
建設業へ留まるにしても異業種への事業転換にしても市場での厳しい競争が待っていることに変わりはない。
2003年12月11日(水)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
国土交通省が建設産業の淘汰再編を全面に掲げたのを請け、各都道府県においても県内建設産業への産業政策を打ち出している。
県としての建設産業ビジョンを示したものから経営改革の取組みへの助成金を創設したもの迄、いずれも「技術と経営に優れた建設会社」を残し、地域雇用を維持するために他分野へシフトさせようとする点で共通だ。
そんな中で山形県のホームページで掲載している県内建設業の振興を目指した「建設産業懇話会」の報告が面白い。
方向性を打ち出したのではなく、その検討の経緯を報告書として公開している。
官学民がメンバーとなって県内建設産業における課題、建設業の業態転換のための進出先に挙げられている農業、福祉、環境の各分野での事業課題と可能性について現実的で実務的な討議を行っている。
当然のことだが地図の上で行き先を示されても、知人もさしたる情報もない見知らぬ場所へ人は簡単に移り住めない。
本来事業はそんなものではないし、裸一貫やってきた経営者なら嫌というほど分かっている。
経営改革は自己責任が原則だが、これまで基幹的な役割を担い、恐らく大多数の都道府県において相当の規模を有する建設産業の構造転換は、発注機関としてだけではなく地方行政としても自らの大きな課題であることは疑いがない。
横並びの指針やビジョンを示して良し、とは行かない筈だ。
現実問題として地域性も含め社会的な課題、法律や制度上の制約も出てくる。
そうしたことへ具体的に対応する環境整備や行政支援があって始めて産業転換のような一大事業は方向付けられるものではないだろうか。
同様に「技術と経営に優れた建設会社」と言う表現にも曖昧さを禁じえない。
現行制度の中で具体的に目指す「優れた技術と経営」の姿を見失っている建設会社は多い。
工事量と工事価格の縮減の中で、「価格」のみが基準となっているのが現実だ。
要求仕様が同じ中でどの様に技術と経営の優秀性を発揮すればよいのか。
そうした面からも技術や品質を考慮する多様な入札制度の導入は急がれる大きなテーマだが、まだまだ環境が整っていないのも現実だ。
また「技術と経営に優れた」とは、発注者としての業者管理の視点では淘汰再編の中で残るべき企業の選別基準であり、個別の発注では正に発注条件。
いずれもそれぞれの面からの明確で具体的な要件提示がなされるべきであり、それを示すことが供給サイドである建設会社の目指すべき経営努力の方向に繋がるものとなろうし、市場形成の競争要件ともなる。
もともと入札制度は選別方法であってQCDS(品質・コスト・工期・安全)を最低限担保する仕組みと併せて機能してきており、技術や品質などに基づく優劣評価は行わないのが原則だ。
‘クサビが外れれば’価格オンリーの非情な戦いとなるのは当然とも言える。
「脱ダム宣言」で話題を呼んだ長野県知事は、地方の建設業界ではすこぶる評判の悪い悪代官のように陰口を叩かれている。
脱ダム宣言に代表される建設行政がドラスティックだったこともあり業界の歴史や慣習を蔑ろにし、厳しい受注競争へ追いやり淘汰しようと悪事をはたらいている姿に映る。
一方でダムの目的を代替させる環境に配慮した新たな利水治水手段を研究するなど、県として先進的な取組みをしていることの評価は高い。
国土計画に沿って単にダムづくりを進める事業者と、ダムは否定したが‘ダムを必要とする目的には向かい合った’事業者との相違が見えてくる。
ダムを施工する高度ではあるが平準化された技術ではなく、地域特性や自然環境へ配慮しつつ事業目的を実現するソフトやハードを組み合わせた代替技術への取組みが今後は顧客ニーズになるだろう。
まだ過渡期なのだろうが、こうした地方の発注者ニーズが明確な競争要件として具体化され提示されていくことに期待したい。
地域が地域としての特性とまちづくりに向かい合えば金太郎飴の都市化政策や横並びの土木建設事業から脱却していくのは当然ではないだろうか。
例えば地域要件をひとつ取っても単なる所在地の限定ではなく、地域の自然環境や風土、伝統技術等々による条件が必要になってこよう。
そうした発注者サイドのニーズが明確な競争要件となって提示されることが、地場産業としての建設会社の「優れた技術と経営」を導くことになるだろう。
地域が地域としての存在意義を明確にし復活する過程に建設会社の新しい姿が隠されている気がしてならない。
地域の復活に不可欠な建設会社の姿にしていくことが悪代官の企みであると思いたい。
2004年2月19日(木)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
リストラクチャリングはリストラの呼称で一般に広く知られている。
マスメディアや日常語としては人員削減の代名詞として使われるため、業績不振企業の「苦肉の策」のような負のイメージが強い。
しかしながら本来の意味は、不採算事業を整理するようなマイナスな取組みを言うのではなく、成長性や強みのある事業へ集中し、事業全体の最適化を図る手法を指している。
人件費の削減が手っ取り早いコストダウンなのは誰でも知っている。
年功序列と終身雇用が象徴の日本的経営の崩壊と騒がれ、聖域に手を付けたことが大きく取り上げられた時にはまだよかったが、こちらも日本的と言えるが一度やってしまうと慣れっことなって常態化してしまう。
日本的経営の看板を降ろす無念さのようなものを最初はヒシヒシと感じたものだが、今では早期退職に逆に社員が群がる光景すらある。
最適化を図るために事業を組み立て直すポジティブな活動がリストラクチャリングである。
その過程で優先度から判断した整理が行われる。
一般に使われるリストラの略称は正に整理に伴う負の面のみを指し示していると言えるが、組み立て直すことを重視しなければならない。
つまりどう組み立て直すかが先になければ、「捨てる」だけになってしまう。
多くの日本の企業で行われたリストラは「捨てる」だけのものであったと言われている。
これを戦略なきリストラと言う。
戦略には経営の意思が必要だ。
いかに組み立て直すかが追及すべきテーマであり、そのために取り組まなければならないのが社長のリストラクチャリングである。
そう、経営者自身を組み立て直すのだ。
地場建設会社に多くみられるように建設業はオーナー経営が多く在籍期間が長い。
オーナー経営の良さは意思決定が早く、企業の方針や経営者のネットワークが長期に継続するため、営業環境や従業員のマインドも安定しやすい。
一方で、制度疲労が生じやすく活性化しにくい。
人事も滞留しがちであり若返りせずチャレンジ志向が失われていく。
様々な改善への取り組みもしてきたのだろうが、一人の人間である以上長きにわたりクセがでるのは致し方ない。
今や待ったなしの業界状況で、惰性の取組みは返って危機の増幅となろう。
だからこそ、自身で「捨てる」ことが必要だ。
社長が経営そのものなのだ。
社長の自己改革を欠いて何かが進むだろうか。
ある地場ゼネコンの社長は、辞めて責任を取ることのできない重責を嘆いた。
大手企業のトップが自身の首を代償に事を収める慣例をなじったのだ。
賛同する方も多いのかもしれない。
例えばこうした考えもリストラの対象となろう。
つまり社長が永遠の責任を取る会社の役職員が仕事への強い責任感を涵養するだろうか?また永遠の社長を前に経営感覚を持った社員が存分に育つだろうか?自社に人材が満ち足りたことがあっただろうか?
もともと現場仕事は徒弟制。
‘金’と‘施工’の分かる代理人が育てば御の字の建設会社も多い。
マネージャーらしい仕事をする人材は決して多くはないのが実情だ。
「永遠の責任」という考えをリストラクチャリングのターゲットとすることは経営責任への社長の強い意志を否定するものではない。
社長への信頼感を生む素晴らしい面も確かに多い。
但し、逆から見た時に何が見えてくるのかが重要だ。
そこにこれからの厳しい経営環境を生き抜くための経営課題がないのかを追求する。
要は当たり前と考えていた事やその考えが浸透した会社の姿をリストラクチャリングのターゲットとして捉えていくことで再構築の姿を描いていく。
またこれまで経営の監視機能があっただろうか。
監視機能がないと言うことは「暴走」と同時に「何もしない」「効果のない」ことも制約されない、つまり取り組んだ結果への評価もないと言うことだ。
一般には監視機能の不在は甘えを生み、成長や改革の阻害要因となる。
社長のリストラクチャリングは「自省」による監視機能とも言える。
場合によっては本当に自らの勇退を決断することになるかもしれない。
しかしそうした厳しさを通じて得られる明確な問題提起が再構築を実現していくには不可欠となるだろう。
未だ続く厳しい建設業界にあって、リストラクチャリングを単なる「切り捨て」の活動であるリストラに終わらせず、またリストラクチャリングが本来の成果を出すためにも、経営者自らがまず自身の経営に対して厳しいリストラクチャリングを施し、再構築の姿を描くことが求められる。
ひとつひとつの仕事の課題への答えは経営の中にあり、そして経営の問題への答えは社長の中にある。
課題はいつでも一つ上の次元の中に答えがあるものだ。
2004年3月3日(水)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)
報道によると価格協議方式の導入が国土交通省所管の公団等で増えていると言う。
年々減り続ける公共建設投資は、事業費の縮減に始まり事業自体の選別、更にもう一歩進んで個々の事業発注時点つまり購買段階でのコストダウンへと民間企業並の手法導入を模索しつつあるようだ。
建設市場を形成する主要なバイヤーが、ビジネスライクなスタンスを取ることは競争市場の健全化と活性化には不可欠なことだ。
今のところ官庁が直接行うには会計法の制約があるようだが、非常に大きな転換点となるものと考えられる。
一般に購買段階におけるコストダウンでは、品質や量とのトレードオフの関係を如何に最小化するかがネゴシエーションのポイントとなる。
単純な‘価格たたき’ではなく良質なものを適正価格で購入するためには、これまでの入札制度では不問であった技術や品質の優劣が課題とならざるをえない。
そのためには技術や品質を担保する客観的で公平な制度づくりが必要となり、発注者による明確な技術及び品質要件の提示とそれらに基づく建設会社の選別という競争市場らしい姿が見えてくる。
そして、そうした競争市場を支える各種の制度においても整備が必要となろう。
例えば中小から大手まで約20万弱の建設会社が一律の評価基準で計られる経営事項審査は、決して技術や品質の面から建設会社を格付けするものとはなっていない。
従来の公共事業の確実性を担保するには適していても価格協議方式に相応しい制度とは言い難い。
新しい試みが成果を出すためには、常に目的に対応した手段へと制度の改革を伴うことが不可欠だ。
思えば公共工事の電子入札に違和感を覚える人は少なくないのではないか。
仕様があるとは言え何十億もの工事を交渉もなくクリックひとつ、価格のみで決まってしまうビジネスプロセスは、民間企業では見当たらない。
手間ヒマ掛ける必要あるものには充分なプロセスを踏むことが求められる。
こうした面からも一律を脱し目的に合致した入札プロセスを検討することも必要だ。
電子的なプロトコル(規約、手順)ばかりではなく、事業に適したビジネスプロトコルが追求されなければならない。
箱造りは進んでも入れる中身が追いついていない。
技術や品質の優劣評価には常に大手建設会社への偏りへの不安が付いて回る。
建設技術の平準化は公共工事には必須要件だが、現実には大手と中小の技術格差は大きい。
一律の技術評価にあっては当然中小建設会社に歩はない。
但し、必要とされる技術や品質の明示に加え、地域要件が加味されれば中小建設会社の存在意義は生れてこよう。
そこに求められるのは、大都市圏からの所得の再配分としての公共事業が立ち行かなくなり、全国一律の都市化政策から地域の特色あるまちづくりへと軸足が移るときの問題解決を担う姿だ。
地域の伝統、文化、風土、自然に基づく地域要件は、所得の流出を防ぐ‘紐付き’とは違い、地域のまちづくりにおいては要求性能、要求品質として求められて然るべきものとなろう。
また高度な建設技術の開発ではなく、伝統技術の発展改良や地域特有の素材を用いたニッチな資材の開発などでは中小建設会社に強みが出てくる筈だ。
まずは地域が明確なニーズを掲げることから始まる。
そのために汗をかく発注者責任もある。
産業政策の基本原則は、市場に任せ、市場原理が働かないところを補完することにある。
企業の自主性が基本だ。
但し、建設産業は市場の大口顧客が公官庁であり、バイサイドと政策サイドの両面を合わせ持つ。
それは豊富な国家建設を滞りなく確実に実行するシステムの構築には優れて効果的に機能してきたと言える。
事業量が減り、公共事業の役割や内容も変わりつつある中、次はこれまでのシステムを造ったバイサイド自らによる創造的破壊が、新しいイノベーションのプライオリティとなろう。
広い意味でのこれまでの産業政策の大きな目的と成果は、雇用調整局面において失業を極小化してきたことにあったのかもしれない。
景気対策の名の下の公共事業もその役割に多大な貢献を誇った。
しかしもう地方への所得配分も潜在失業者の企業内留保も立ち行かなくなってしまった。
それでは、と産業転換へと舵を切っても、もともと高齢化産業、他分野へ転出する気力も体力も疑わしい。
彼方の分野も豊饒の地か?それよりも経験やノウハウを新しい知識や技術の創造へと役立つ知識労働への転換の方が現実的ではないか。
先人の知恵が生きやすいのも建設産業の特徴だ。
そのためにも従来型の産業システムや画一的な事業から脱皮し、企業のイノベーションを促進する競争市場の確立が先決と思える。
2004年4月5日(月)掲載
日刊建設工業新聞コラム「所論/諸論」より(1年間連載したものに一部加筆訂正)

|
||
|
第1回 JVの基本1 (とても重要なJVの基本について) 第2回 JVの基本2 (JV会計の4つの基本原則について) 第3回 JVの受注 (JV工事受注前後の運営と会計について) 第4回 JVの経費 (様々なJVの経費について) 第5回 JVの定時支払(JVの定時支払について) 第6回 JVの購買 (JVの購買業務について) |